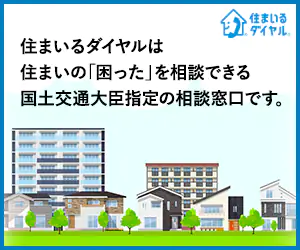一級建築士が解説!中古住宅やリフォームの「困った」を解決するには?
「希望の条件に合った中古住宅を見付けて、理想の住まいにリフォームしたい!」と思う方も多いのでは。でも、よい中古物件を見極めるにはどうすればいいのでしょうか。また、購入後やリフォーム後に万が一不具合が発生した場合、補修対応でもめてしまうという可能性も。中古住宅購入やリフォーム実施の際にチェックしたいことと適切な対応について住まいのプロにお聞きしました。
提供:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
お話をうかがった方

マンション設計に携わった経験を数多く持つ一級建築士が、住まいの性能を解説。性能評価申請に関わったマンションは20棟以上。設計事務所設立後は子育ての経験を生かし保育園の設計なども行う。その他に戸建て・マンション購入セミナー講師、新聞へのコラム連載など。
トラブルを防ぐために!中古住宅の購入とリフォームを計画する際に気を付けたいことは

新築と比較して価格が安いなど、メリットのある中古住宅。中古住宅を購入してリフォームする場合、どんなことに気を付けるべきなのでしょうか。中古物件を選ぶ時の注意点や、リフォーム前に確認するべきポイントを一級建築士の井上恵子さんに伺いました。
井上さん(以下敬称略)「中古物件を探していると、どうしても価格帯や立地条件に目が行きがち。ですが、建物の状態をチェックすることがとても大事です。実際に建物を目で見て、しっかりと確認しましょう。
例えば、壁や天井に結露や水漏れの跡がある場合、断熱材に不具合がある可能性や、雨漏りをしている可能性があります。中古住宅を購入する際のチェックポイントを解説するサイトもありますので、参考にしてみては。
また、目では確認できない部分も、必要な情報があればある程度確認できます。例えば、建築確認日を調べれば、その建物が「旧耐震基準」なのか「新耐震基準」なのか判別できます。ただし耐震性を判断するには、しっかり施工されていることが前提。手抜き工事は見抜けません」

そこで、「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」に加入している中古物件を選べば安心と、井上さんは話します。
井上「瑕疵とは、欠点・欠陥のことを言います。そして、既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。この保険に加入するには、原則として新耐震基準に適合していることと、第三者機関の建築士による検査を受けて合格することが必須。万が一、保険に加入している物件を購入後に『構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分』に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができます。
中古住宅を購入してリフォームを行う場合、リフォーム工事部分の瑕疵も含めて保証がつくタイプの保険もあります。また、現在お住まいの住宅にリフォームを行うときは、『リフォーム瑕疵保険』への加入がおすすめ。万が一、リフォーム工事に瑕疵が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができます。また、住宅瑕疵担保責任保険法人の審査を受けた登録業者のみが扱える保険のため、登録の有無をリフォーム会社選びの指標にもできます」
さらに、中古住宅の購入前にチェックしておきたい項目を教えていただきました。
井上「検討する中古住宅に、適切な時期に適切なメンテナンスが行われてきたかを確かめましょう。リフォームやメンテナンス時の履歴を記録した「住宅履歴情報」があると、より安心です。
また、地震や近年頻発する台風や豪雨など、災害についても考慮すべきです。事前に河川の氾濫や地盤の状況を、確認しておきましょう。国土交通省が運営する「わがまちハザードマップ」から、各自治体のハザードマップを調べることができます」
また、希望通りのリフォームを実現するには、物件購入時にリフォームしやすさをチェックすることもポイントです。
井上「例えば、木造の在来工法は壁の移動がしやすい構造、対して、ツーバイフォー工法は壁の移動が難しい構造と言えます。そのため、もし間取り変更を伴う大規模なリフォームを希望するのであれば、在来工法の家を選んだ方が良いかもしれません。
せっかく住宅を購入したのに、思い描いたリフォームができなかったり、予期せぬ補強工事の追加費用で予算オーバーになったりしないようには気をつけたいもの。また、リフォームの費用が妥当であるかは、数社に見積もりを取って比較すると判断しやすくなります。それでも、多くの人にとって見積もり内容のチェックをすることは難しいと思います」
そこで、国土交通大臣が指定する住宅専門の相談窓口である『住まいるダイヤル』のホームページで、リフォーム見積書セルフチェックのポイントを参考にしてはいかがでしょうか。受け取った見積書に関して相談したい場合は、契約前であればリフォーム見積チェックサービス(無料)も活用できます。一級建築士の資格を持った相談員が電話でアドバイスしてくれます。
そんな『住まいるダイヤル』には年間約3万件もの住宅に関するさまざまな相談が寄せられています。安心して快適に暮らすためにも、中古住宅やリフォームに関する相談事例について見てみましょう。
CASE:外壁をリフォームしてまだ1年なのに、剥がれ、ひび割れ、ふくれなどが発生!補修費用も心配です

屋根や外壁のリフォームは足場をかける必要があることから高額になることが多く、その耐用年数は約10年と言われています。そのため1年で不具合が起こるのは、施工不良であることが予想されると井上さんは話します。
井上「考えられる原因としては、塗装後の乾燥不足や、塗装前の洗浄が不十分で汚れが残っていたこと。ほかにも、既存のシーリング材を剥がさずに上から塗装を行ったことや、塗装の手順や塗料の希釈濃度など正しい仕様が守られていなかったことなどがあげられます。
まずは、施工業者に連絡して、現状を確認してもらいましょう。また、契約内容通りの工事がされていない可能性もあるので、契約書や見積もりに記載されている内容の確認も必要です」
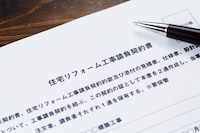
基本的には、施工業者がスムーズに対応してくれるものだそう。でも、万が一、施工業者が対応しない場合や追加費用を請求されるなどのトラブルになった場合には、どうすればいいのでしょうか。
井上「その場合は住宅トラブルの相談に対応してくれる、第三者機関の利用をおすすめします。外壁が剥がれるとそこから雨水が入り込みやすく、家が傷む原因になりやすいため、速やかに対応することが大切です」
『住まいるダイヤル』なら、一級建築士の資格を持った相談員が、公正・中立な立場から相談を受け付けているので安心です。
困ったときに頼れる「住まいるダイヤル」とは?

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは、「住宅品質確保法」「住宅瑕疵担保履行法」に基づいて、消費者の利益保護や住宅紛争の迅速・適切な解決を図るために、住宅相談、紛争処理の支援などの業務を幅広く行っています。住宅専門の相談窓口となる『住まいるダイヤル』は、累計40万件以上の電話相談に対応した実績をもとにした、多様な事例をホームページで確認することができます。
井上「自分が悩んでいる内容と類似する事例を検索すると、その解決方法やアドバイスも書かれているのでとても参考になります。より詳しく知りたいのであれば、無料の電話相談も利用可能。電話相談では解決が難しい場合も、全国の弁護士会と連携した、弁護士と建築士による対面相談「専門家相談」の制度があります。
万が一、トラブルが裁判にまで持ち込まれるような状況になると、時間やお金、精神的にも負担が大きいことでしょう。『住まいるダイヤル』が支援する業務には、住宅についての紛争に関する専門家が公正・中立な立場で関与し、裁判よりも迅速で、話し合いで合意に至るように解決を図れ、しかも、申請手数料1万円※1のみで利用できる「紛争処理」という制度もあります」
そして、2022年10月の住宅瑕疵担保履行法の改正により、住宅トラブルを専門家に相談できる制度「専門家相談」、専門家の関与による住宅トラブルの解決手続「紛争処理」の対象が拡大されています。
>>支援制度の対象拡大についてもっと詳しく
井上「今回の改正では、サポートの対象が新築住宅だけでなく、瑕疵保険が付された中古住宅やリフォーム工事も対象に。中古住宅を購入してリフォームをしたい方に、さらなる安心感がプラスされました」
新築2号保険・リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険・既存住宅売買瑕疵保険・延長保証保険が今回の拡大範囲※2。住宅を壊して造るスクラップ&ビルドではなく、住まいを大切に長く使い続ける。それは、脱炭素社会という環境への貢献へもつながります。
井上「これまでの中古住宅の売買は、あいまいで不安な面が大きかったのも事実です。これからは、保険加入を目安にすることで良質な中古住宅を選びやすくなるのでは。また、安心して自分らしい住まいにリフォームもしやすくなるでしょう。みなさんがより良い住まいに出会うための、力強いサポートになるのではと期待しています」
>>住まいの「困った」が解決できない時は、住まいるダイヤルへ
※1:一部、申請手数料が1万4千円となる場合があります。
※2:2022年9月30日以前(改正法施行前)に上記保険に加入している場合もご利用いただけます。