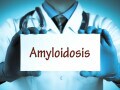脳科学・医薬ガイド薬剤師阿部 和穂
あべ かずほ薬学博士・大学薬学部教授。脳科学と薬理学を専門とする研究者
東京大学薬学部卒業、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員、星薬科大学講師を経て、武蔵野大学薬学部教授。薬学博士。専門は脳科学と医薬。
ガイド記事一覧
鍋が原因で認知症に?アルツハイマー病とアルミニウム原因説の誤り
【認知症研究者が解説】「アルミ鍋が原因で認知症になる」という説が注目され、悪徳商法にもつながるなど社会問題になった時期がありました。この「アルミニウム仮説」、俗にいう「アルミニウム原因説」は誤りだったことが分かっています。その理由について、わかりやすく解説します。
掲載日:2022年11月15日認知症アミロイド仮説が支持される3つの理由と治療薬開発の課題
【薬学博士、認知症研究者が解説】アルツハイマー病によって起こる「アルツハイマー型認知症」。治療薬の開発が世界中で待ち望まれていますが、まだ有効性を示せた薬はありません。治療薬開発の現場で、「アミロイド仮説」が支持されている理由、それにも関わらずまだ有効な薬が見つかっていない理由についてわかりやすく解説します。
掲載日:2022年11月14日認知症「無添加」表示の規制が厳格化…無添加食品の真実とリスク
【薬学博士・大学教授が解説】「無添加」と書かれた食品は体にいいと思っていませんか? 味噌や醤油、離乳食などさまざまな製品があるようですが、実は無添加表示にはこれまで基準や決まりがなかったため、何が無添加かという肝心の情報が書かれていない製品も少なくありません。上手に安全な食品を選ぶための考え方を解説します。
掲載日:2022年11月11日食生活・栄養知識全身性アミロイドーシスとは…症状・治療薬・予防法
【薬学博士・大学教授が解説】私たちの体の15~20%はタンパク質ですが、「アミロイド」と呼ばれる異常なたんぱく質が溜まることで、さまざまな病気が引き起こされます。それらの病気の総称が「アミロイドーシス」です。今回はアミロイドとは何か、全身性アミロイドーシスの症状と治療法について、解説します。
掲載日:2022年11月08日薬小学生が大麻使用?未成年の逮捕者も…薬物乱用の危険性をどう伝えるべきか
【薬学博士・麻薬研究者が解説】小学生の大麻使用の報道や、中高生が大麻所持などの疑いで逮捕される事件が増えています。これらの青少年は、喫煙や飲酒経験がある割合も高いようです。よく「大麻とタバコはどちらが危険か」という比較を見かけますが、薬物の有害性の比較は無意味です。子どもたちの安全と健康を守るために、伝えるべきことは何かを考えてみましょう。
掲載日:2022年11月07日依存症アルツハイマー病を発症するのは人間だけ?動物に認知症はないのか
【認知症研究者が解説】認知症になるのは、人間だけでしょうか? 他の動物も年とともに脳が衰えるため、イヌやネコにも「ボケた」行動が見られることがあります。しかしアルツハイマー病になるのは人間だけです。人間と動物の違いの研究が進めば、人間だけがなる認知症の謎が解明できるはずです。
掲載日:2022年11月05日認知症自然食品は体にやさしい?「人工物は有害」という考えが危険なワケ
【薬学博士・大学教授が解説】食品を選ぶときに「天然」「自然」という言葉を判断材料にしていませんか?「自然なものは安全でやさしく、人工物は有害」という考えは、大きな誤解です。自然の物の危険性、人工物の安全性も正しく知った上で、上手に判断することが大切です。
掲載日:2022年11月04日食生活・栄養知識アミロイドβタンパクとは…アルツハイマー病の原因物質と考えられている理由
【認知症研究者が解説】アルツハイマー病の根本的な治療薬の開発が待ち望まれています。発症の原因物質は「アミロイドβタンパク(Aβ)」だと考える「アミロイド仮説」に基づいた医薬品の開発が進められていますが、有効性が実証できた薬はまだ見つかっていません。そもそもアミロイドβタンパクとは何か、なぜ原因物質と考えられているのかをわかりやすく解説します。
掲載日:2022年11月04日認知症「降圧剤で認知症になる」は本当か?血圧を下げる薬の副作用の真偽
【大学教授・認知症専門家が解説】「血圧を下げる薬で認知症になる」「降圧剤の副作用で認知症リスクが上がる」といった話があるようですが、本当でしょうか? 認知症予防のために血圧を下げる薬は飲まなかった場合、逆に認知症リスクを上げる恐れがあります。一方で、血圧の下げ過ぎも危険です。わかりやすく解説します。
掲載日:2022年11月04日認知症コラーゲンの危険な一面…膠原病・肺線維症など、命に関わる病気との関連も
【薬学博士・大学教授が解説】コラーゲンは「美と健康に欠かせない物質」ではありません。体内のコラーゲンが増えすぎることで、肺線維症や肝硬変などの命に関わる病気になることもあります。コラーゲンを過剰に摂取する必要はない理由を、わかりやすく解説します。
掲載日:2022年11月03日食生活・栄養知識
その道のプロ・専門家約900人
起用ガイドが決まっていない方はこちら