特に住まいという大きな決断を前に、「頑丈なマンションだから」「高層階だから水害は関係ない」といった分かりやすい安心材料に頼りたくなるものです。しかし大切なのは安心感に安住するのではなく、起こりうるリスクに賢く備えるという視点です。その鍵は、建物を支える「土地」そのものを正しく知ることにあります。
その見極め方について、個人向け不動産コンサルティング事業を展開する株式会社さくら事務所の田村啓氏が詳しく解説します。
地図を使って土地の素顔を読み解く
物件の災害リスクを調べる最初のステップが、ハザードマップの確認です。国や自治体が公開する、防災の基本図で、その土地で想定される洪水や土砂災害、津波などの危険度を地図上で視覚的にチェックできます。多くの方がまず確認するのは、自宅周辺がハザードマップでどう色分けされているかという点でしょう。ここで大切なのは色の有無だけでなく、リスクの「種類」と「程度」を正確に読み解くことです。例えば、同じ浸水リスクでも、
・堤防決壊で家屋ごと流される危険性がある
『家屋倒壊等氾濫想定区域』のエリア
・垂直避難(上階への避難)で命の安全を確保できる可能性がある
『内水氾濫で浸水深50cm』のエリア
この2つでは、その意味合いはまったく異なります。
特に低層階を検討している方や、高齢者などご家族に配慮が必要な方がいる場合は、このリスクの質の違いが避難計画を大きく左右することを理解しなければなりません。
ハザードマップだけでは足りない?地理院地図というもう1つの視点
さらに、精度を格段に高めてくれるのが、国土地理院の地理院地図です。ハザードマップを天気予報とするなら、こちらはその予報の元となる天気図に当たるもので、ハザードマップだけでは見えないリスクを教えてくれます。 というのも皆さんが日々参考にする天気予報は、あくまで天気図の解釈の1つに過ぎません。これはハザードマップも同じ。特に、シミュレーションの対象になっていない小さな川の氾濫リスクなど、危険性が見過ごされている抜け・漏れの可能性があるのです。そこで地理院地図を使い、土地の微細な高低差や、その土地がかつて川・沼地・崖、あるいは盛り土で造成された場所だったのではないかという「土地の履歴」まで読み解きます。ハザードマップで色がついていなくても、土地の履歴を遡ることで、初めて見えてくるリスクがあるのです。
雨の日こそ要チェック!歩いて見えるリスクの兆候
地図を確認したら、次は現地を歩いてみましょう。車では気付きにくい、ちょっとした坂やくぼみなどを体感でき、地図だけでは分からないリスクを発見するきっかけになります。おすすめは「雨の日」の確認です。面倒に感じられるかもしれませんが、土地が持つ水に関する性質は雨の日にこそ、その本当の姿を現します。地図では読み取りにくいわずかな高低差が、実際の水の動きにどう影響するのかなど、晴天では分からないポイントを確かめる絶好の機会となります。地域の排水能力や敷地の水はけの良しあしを判断するために、次のような点確認しておきましょう。
- 道路の冠水:前面道路や周辺の道路は水浸しになっていないか
- 敷地への水の流入:道路から敷地に向かって、水が流れ込んでいないか
- 水たまりのでき方:エントランス周りや駐車場のどこにどの程度の水たまりができるか
- 排水溝の状態:側溝や排水マスから水があふれていないか
※擁壁(ようへき)とは、崖や盛り土などの側面が崩れるのを防ぐために造られる、コンクリートブロックなどの壁状の構造物
<見た目のチェック>
大きなひび割れや、壁面が前に膨らみがないか。壁が膨らんでいる状態を、専門用語で「はらみ」と言います。ひび割れや「はらみ」は、擁壁が劣化している、あるいは内部から想定外の圧力を受けている危険なサインです。
<水のチェック>
「水抜き穴」が詰まっていたり、穴以外の場所から水が染み出ていたりしないか。水抜き穴は擁壁の命綱であり、機能不全は崩落の原因となり得ます。
土地の高低差、雨の日の水の流れ、そして擁壁の状態。こうした現地でしか得られない生の情報が、ハザードマップの情報を補い、より確かな判断を可能にしてくれます。
マンションだからこその「ライフライン」リスク
さて、ここで冒頭に触れた「高層階であれば水害の心配はない」という安心感に立ち返ってみましょう。確かにお部屋自体が直接浸水する可能性は低いかもしれません。しかし、そこに立ちはだかるのがライフラインの脆弱性という、マンション特有の問題です。考えてみると、マンションの電気設備(受変電設備)や給水ポンプ、そして全戸の水をためる受水槽は、多くが地下や1階に設置されています。
もし、これらの設備が浸水被害に遭えば、建物全体が停電・断水します。エレベーターは停止し、トイレが使えなくなることもあります。たとえ10階の自室が無事でも、生活は一瞬で立ち行かなくなり、高層階は陸の孤島と化してしまうのです。
また、液状化が発生した場合、杭基礎で支えられた建物自体は無事でも、周囲の地面だけが沈下してガス管や水道管が断裂し、ライフラインが長期間使えなくなる可能性もあります。
マンションの場合、自宅で安全を確保する在宅避難が基本となります。しかし、それはライフラインが停止することを前提とした備えがあってこそ成り立ちます。
ハザードマップの想定浸水深と、マンションの重要設備が設置されている階層を照らし合わせるなど、物件ごとのリスクを具体的に把握しておくことが、いざというときの備えの第一歩となります。リスク把握というひと手間と、最低限の飲料水や簡易トイレなどの備蓄。この両輪があってこそ、本当の意味で暮らしを守れるのだと心得ておきたいものです。
まずは土地を知ることが第一歩
日本に住む以上、災害リスクがゼロの土地を見つけることは現実的ではありません。大切なのは、リスクを過度に恐れるのではなく、その土地にどのようなリスクが、どの程度存在するのか、を客観的に把握し、そのリスクとどう向き合っていくかを考えていくことが大きな意味を持ちます。ハザードマップの一歩先を読み解き、現地で地形や擁壁の状態を確かめ、ライフラインの脆弱性を理解する。こうしたスキルは、これからの住まい選びに不可欠なものとなっています。
もちろん、ご自身で全てを調べるのは難しいと感じるかもしれません。その場合は、私たち専門家が提供する「災害リスクカルテ」といった客観的な診断リポートを、判断材料に加えていただくのも選択肢となります。
住まい選びは、未来への大きな投資です。そして、その土地のリスクを「知る」ことは、ご自身の資産と暮らしを守るための、最も重要で確実な一歩と言えるでしょう。
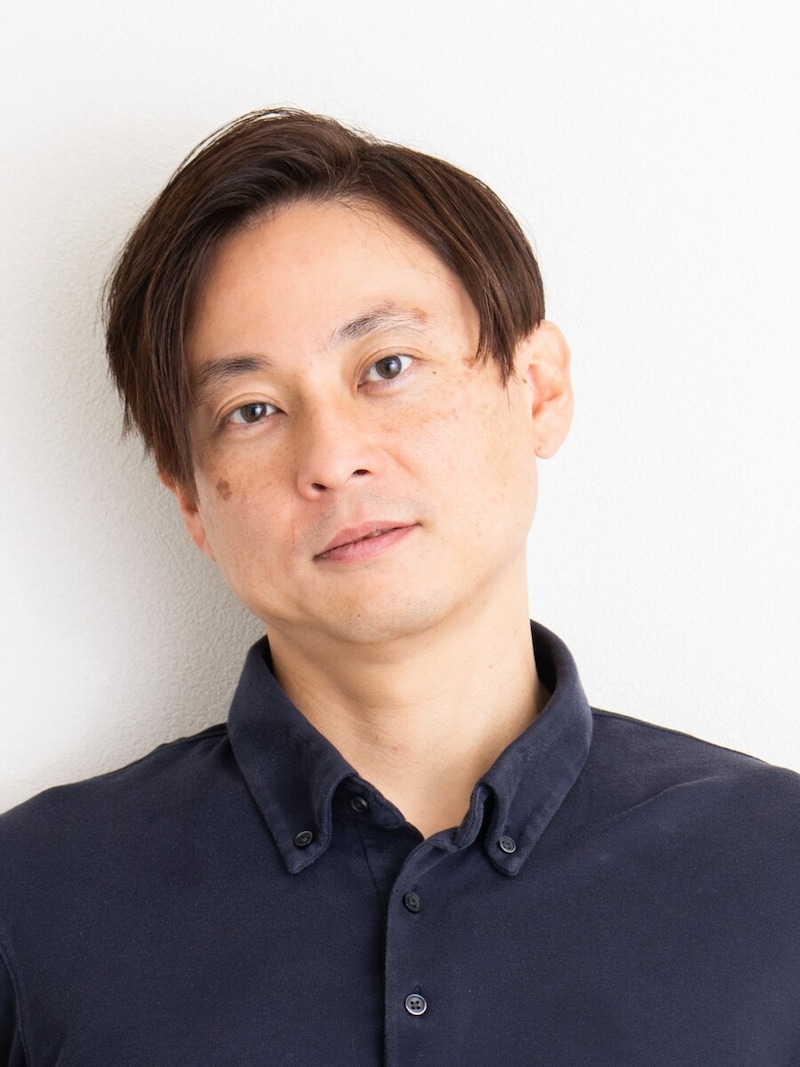
株式会社さくら事務所執行役CRO田村氏
文:株式会社さくら事務所 執行役CRO 田村啓
大手リフォーム会社での勤務経験を経て、さくら事務所に参画。建築の専門的な分野から、防災の分野まで幅広い知見を持つ。多くのメディアにて広く情報発信を行い、NHKドラマ『正直不動産』ではインスペクション部分を監修。







