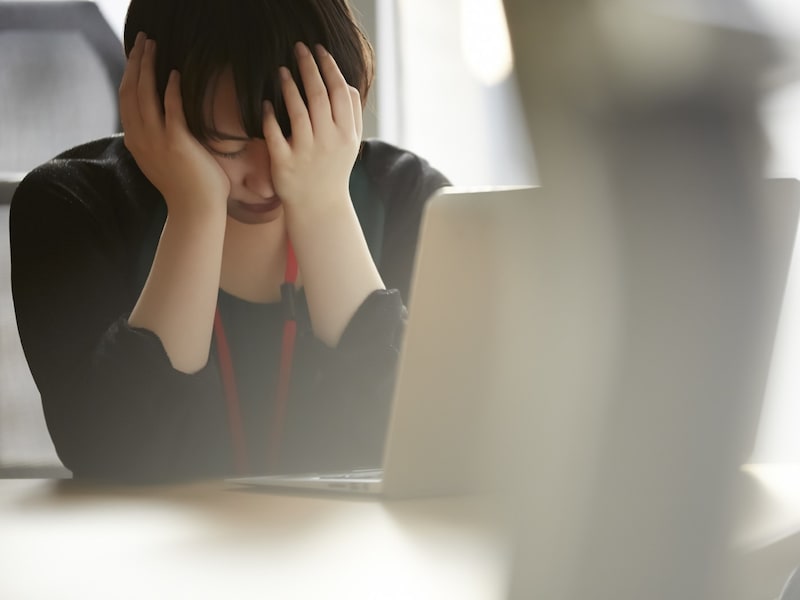20年以上プロジェクトマネージャーを務めてきたプロジェクトのプロ・橋本将功さんの著書『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン 50』では、良かれと思ってやっているマネジメントが、実は部下を追い詰める「アンチパターン」になっている危険性を指摘しています。
今回は本書から一部抜粋し、担当者のモチベーションを奪い、最悪の場合「燃え尽き症候群」を引き起こすフィードバック不足の問題点と、その背景にあるマネージャーと担当者の「目線の違い」について紹介します。
現代の労働は「精神労働」
現代は単純なルーチンワークで企業が利益を出したり、競争相手に打ち勝っていくことが難しい時代です。サービスや商品を提供する際には、そこに顧客が評価できる「付加価値」が求められるようになっています。
この付加価値を生み出す労働には、多くの試行錯誤が必要とされ、頭脳労働というよりは「精神労働」と呼べるようなものです。
特に、より高い付加価値を生み出すために、新規事業などで競合他社や業界全体でまだ他に類のない取り組みを行おうとする場合は、それらを実現するための検討やアウトプット作成作業は「正解のない物事への取り組み」になるため、担当者は多くの不安や葛藤を抱えながら実施することになります。
しかし、そうして取り組んだ成果としてのアウトプットが評価されることなく放置されると、作業を行った担当者はモチベーションを大きく低下させることになります。
部下が「燃え尽き症候群」になってしまう原因は?
世の中では一般的に行われている取り組みでも、自社で前例がない場合、それを実行する担当者はリスクを取りながら仕事を進めることになります。特に既存業務が仕組み化されていて「成功することが当たり前」という考え方が支配的になっていたり、個人の成果や評価が出世競争に強く影響したりする社内文化の組織では、成功するかがわからない取り組みに対する理解が低いことがあります。
こうした組織では、新しい取り組みで失敗すると、評価を大きく下げることになったり、周囲から批判を浴びたりするリスクを抱えることになるため、挑戦する人はより多くの精神的な負荷を受けます。
特にプロジェクトとして数ヶ月から数年にわたる取り組みを続ける際は、売上や利益のような形で実績として明確な成果が出るまでに長い時間がかかるため、作業一つ一つのアウトプットに対する評価を得られない場合に、担当者が慢性的に空虚さを抱えることになります。
これが解消されない場合、モチベーションやメンタルの維持が困難となって最終的に「燃え尽き症候群(過度なストレスや負担が長期間にわたって続くことによって引き起こされる心身の疲弊状態)」の原因の一つとなることがあります。
長期間のプロジェクトで、大きなトラブルを抱えることなく順調に仕事をこなしていたように見えていた人が急に会社に来られなくなり、リタイア状態になってしまうケースがしばしばありますが、これは「何のために日々心を砕いて仕事をしてきたのかわからない」という心理状態が誘因となっていることがあります。
「仕事だから黙ってやれ」はNG
担当者のアウトプットに対して適切なフィードバックを示さないマネージャーは、しばしば「仕事だから黙ってやれよ」や「仕事の成果は精度が高くて当たり前」という考え方を持っていることがあります。特に叩き上げで黙々と作業を行って成果を出してきた人は無意識にそういった考えを持っており、それが部下やメンバーへの話し方や態度に出る傾向があります。
他人から細かいフィードバックを与えられなくても新しい取り組みを行って成果を出す人は、そこが評価されてマネージャーに抜擢されることもあるため、そういう人には理解しづらいことかもしれませんが、多くの人にとってはうまくいくかどうかわからない取り組みをフィードバックなしで継続することは難しいことなのです。
また、適切なフィードバックが提供されない背景には、マネージャーと担当者の「目線」の違いも大きく影響します。
作業を行う担当者が仕事をする際に最も気にするのは「自分の仕事(アウトプット)がどのように評価されるか」ですが、マネージャーが最も気にするのは、自分がマネジメントするプロジェクトや部署が最終的に提示する業績(売上や利益など)や成果(業務フローの整備やWebサービス、アプリなどのITプロダクトのリリースなど)になるでしょう。
つまり、マネージャーにとってはプロジェクトの成果はあくまでもスタート地点に過ぎませんが、関わっているメンバーにとってはそこにたどり着くまでのプロセスが自分自身のモチベーションやキャリア設計の維持と形成に極めて重要な要素となるのです。
そして、この目線の違いがアウトプットに対するフィードバックの欠如につながるのです。
橋本将功(はしもと まさよし)プロフィール
パラダイスウェア株式会社 代表取締役 早稲田大学第一文学部卒業。文学修士(MA)。大学・大学院ではイスラエル・パレスチナでテロリズムの調査研究を実施。IT業界25年目、PM歴24年目、経営歴15年目、父親歴11年目。 Webサイト/ Webツール/業務システム/アプリ/ 組織改革など、500件以上のプロジェクトのリードとサポートを実施。世界のプロジェクト成功率を上げて人類の幸福度を最大化することが人生のミッション。著書に『人が壊れるマネジメント』(ソシム、2025)『プロジェクトマネジメントの本物の実力がつく本』(翔泳社、2023)『プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本』(翔泳社、2022)