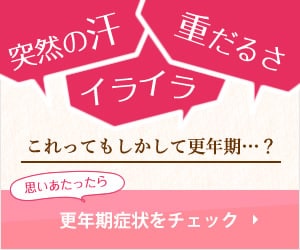子供の受験の結果を大きく左右するのは「母親」だった…!?受験に成功するための秘訣とは
もしかして反抗期…? 思春期の子どもと上手にコミュニケーションを取る方法
思春期になり子どもとの間になんだか距離が…。急に口をきかなくなったかと思えば、「ウザい」などと反抗的な態度を取ることも…。そんな思春期の子どもとの接し方、そして、子どもからのサインを見逃さないための、注意すべきポイントをご紹介します。
提供:小林製薬株式会社
お話をうかがった方

メンタルヘルスの分野を中心に執筆するカウンセラー、ライター。精神保健福祉士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントの資格を持つ。現代人を悩ませるストレスに関する基礎知識と対処法を解説。ストレスやメンタルコントロールに関する著書・監修多数。
反抗の“ウラ”にある子どもの気持ちとは

思春期とは、小学校高学年から中学生くらいの子どもが大人になる準備をする時期と言われています。体だけでなく、心にも大きな変化があるとされ、この時期に親子関係がうまくいかなくなるケースは少なくないようです。
大美賀さん(以下敬称略)「それまでは、親子の関係が子どもにとっても最大の関心事でした。親の言う事はたいてい正しいし、そんな親に褒めてもらいたい、認めてもらいたいという気持ちが強かった。しかし、小学校高学年くらいから、その世界が広がり出し、親子の枠組みという安全地帯から飛び出して社会で生きていきたいという欲求が高まります。その時期の社会といえばすなわち、友達との付き合い。つまり、友達に承認されたいという思いが大きくなるあまり、親への関心が薄れてしまうのです」
つまり、思春期=自立期だと大美賀さんは言います。
大美賀「しかし、それが親の目には“反抗”に映ります。親と関わる時間が減り、詮索すると『うるさい!かまわないで!』などと言う。今まで疑わなかった親の言動を批判的な目で見る……子と親、どちらの視点で見るかによって、同じ状態がこんなにも違ったふうにとらえられてしまうのです。
親にしてみれば、今までそんなことがなかったのに、どうして?と元の関係に戻そうと必死で努力するのですが、それが子どもにとっては過干渉に思えてしまいます。
大美賀「そこで、さらに親との距離を置こうとする。それに親がさらにとまどう…というスパイラルに陥ってしまうのです。そもそも思春期の子どもは、学校や塾などでまわりの友達についていこうと一生懸命頑張っています。承認されているのかいないのかの不安を抱えながら、言葉ひとつ行動ひとつにものすごく気を配っているので、ピリピリしているのです。そんなストレスフルな状態において、親のことなんてかまっている余裕がないというのがホンネ。反抗するとかしないとか以前に、『お願いだから放っておいて』というのが正直な感情なのではないでしょうか」
母親がしてあげられること、してはいけないこと

そんな状態の子どもに、母親がしてあげられることとはどんなことでしょうか?
大美賀「反抗期を迎えた時期に大切なのは、適切な距離を保ちつつ、本当に助けが必要な時には必要なサポートをしてあげられる状態にすることです。いわば、“港”のようなもの。友だちとの社会における冒険に傷つき疲れたら、いつでも帰る拠り所として、変わらずそこにいてくれることで、子どもは存分に自分を試してみることができるのです」
大美賀さんいわく、思春期の子どもに大切なのは、以下の3つだと言います。
1)健康のサポート
栄養の整った食事や質の高い睡眠がとれるよう気を配り、病気やケガをしたら適切なケアをする。子どもは自分が健康でいられるようにしてもらうことで親への信頼につながります。
2)安心のサポート
親自身の生活の変化が激しいなど、環境の変化が多い家庭では子どもの気持ちも不安定になりがち。家族が毎日の生活を滞りなく続けていくことで、子どもは勉強や部活などに安心して集中できるようになります。
3)承認のサポート
家族みんなで食卓を囲んだり、「おはよう」「おかえり」などのあいさつを欠かさずおこなうなど、なにげないコミュニケーションを取り続けることで、子どもは自分がそこにいてもよい存在なんだと思えるようになります。
それ以外のことは多少意に沿わないことがあっても、干渉しないのが一番です。
逆にやってはいけないことは、子どもとのコミュニケーションを完全に絶ってしまうことです。「子どもももう大きくなったんだし、親も子離れしなくては」とばかりに、子どもから目を離してしまうと、子どもは本当に困った時に戻るところがなくなります。
たとえ、以前のように学校であったことを何でも話してくれる関係でなくなったとしても、子どものことをよく見ていれば、困っているサインに気づく可能性が高まります。「食欲もないし、いつもより疲れているような気がする」「よく寝られてない様子。なんだか追い詰められているのかも」などと感じたら、その時こそ母親の出番。多少嫌がられても気にせず、子どもに困っていることはないか尋ねましょう。
要注意! 母親の余裕のなさが子どもとの関係を悪くする

とはいえ、こうしたことに気を配るためには、母親自身が心身に余裕がないとなかなか難しいと大美賀さん。
大美賀「実は子どもが思春期にあたる時期は、親も人生の折り返し地点を迎える時期に合致します。いわば“思秋期”とも言えるこの時期は、人生の目的を失いかけたり、体調に変化が現れることが少なくありません。特に女性の場合、更年期に伴うホルモンの変化もあって、さまざまな不調を抱えたり、わけもなく気分の浮き沈みが生じる時期でもあります。そんな状態のなかでも余裕をもって子どもに接するためには、とにかく頑張りすぎないことが大切です」
仕事や家事など、自分ひとりで抱え込まない。不調だと感じたら休む。自分の症状にあった医薬品などを試してみる……「気持ちだけでは乗り切れないので、具体的な策を講じて」と大美賀さん。
大美賀「反抗期は永遠に続くわけではありません。子どもの状態に一喜一憂しないで、上手に受け流すことも大切です。過ぎ去ってしまえば、『あれは何だったの?』というくらい平和な毎日が戻ってくることも。それを信じて、反抗期、どんとこい!くらいの気持ちで構えていてほしいですね」
毎日の生活のなかで穏やかに更年期の不調の改善
更年期の不調に効果がある医薬品にはさまざまなものがあります。なかでも薬局や薬店で気軽に手にできるものとして100年以上にわたる歴史のある小林製薬の「女性保健薬 命の母A」。
漢方医学の視点から考えられた13種の生薬と、女性が不足しがちなビタミン類をしっかり配合。更年期特有の急な汗やイライラ、重だるさ、肩凝りなどを治していきます。
糖衣錠なので飲みやすく、毎日の生活のなかで穏やかに更年期の不調の改善をめざすことができるのもうれしいポイント。「もしかして更年期?」と思ったらぜひ試してみてください。