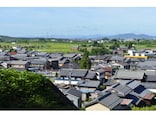ステップ4-A 遺言があった場合
 |
| 名義変更はどのように行なわれるのか? |
遺言の内容により遺留分が侵されていた場合には、遺留分の減殺請求を行なうことができます。その期限は、遺留分が侵されていたことを知った日から1年又は相続開始の日から10年です。
詳しくは >>> 遺言書を取り消したい場合は / 遺留分とは
ステップ4-B 遺言がない場合
遺言がない場合や遺言から漏れた財産がある場合で相続人が複数いるときは、相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。相続税申告のために期限がある場合を除き、遺産分割には期限がありませんが早めに行ないましょう。詳しくは >>> 遺産分割協議の基礎を学ぼう / 遺産分割でもめないためにはどうする?
相続人が1人のみの場合には、戸籍関係の書類をまとめた相続証明書で名義変更が行えます。
ステップ5 10ヶ月以内に相続税の申告・納税
相続税の申告が必要な場合には、相続開始日から10ヵ月以内に相続税の申告と納税が必要です。遺産分割が決まっていなくても、とりあえず法定相続分で取得したものとして申告と納税が必要になります。詳しくは >>> 相続税申告の疑問ベスト5
ステップ6 名義変更
遺言や遺産分割協議書で名義変更をします。不動産は、被相続人の名義のままになっていると売却や取壊しが出来ません。また、トラブル防止の意味でもきちんと名義を変更しておきましょう。名義変更を終えて、相続手続きが終了します。詳しくは >>> 相続財産の名義の変更方法と注意点
【関連記事】
・葬儀のあとに必ずすべき2つの相続手続き
・相続手続きの期限