演歌・歌謡曲 人気記事ランキング
2025年02月04日 演歌・歌謡曲内でアクセスの多かった記事をご紹介します。
1位ロカビリー歌手とは?日本のロカビリーの歴史【50~60年代】
ロカビリーとは和製ロックの原点。しかし日本で"ロカビリー"は誤解され続けてきた。エルヴィス・プレスリー、平尾昌晃、ミッキー・カーチス、山下敬二郎、日劇ウェスタンカーニバル……1950年代~1960年代のロカビリー歌手を解説します。
 和製ロカビリー、オールディーズガイド記事
和製ロカビリー、オールディーズガイド記事2位戦前を彩った歌声の架け橋 李香蘭と永田絃次郎 後編
今回は戦前の歌謡曲シーンを代表する"中国人歌手"李香蘭と、"国民的歌手"永田絃次郎という、数奇な音楽人生を送った二人を紹介。後編では永田絃次郎の持つ圧倒的な歌唱力の魅力、彼が歌った軍歌、戦時歌謡と戦隊・ヒーロー系アニソンの共通性などを徹底解説。
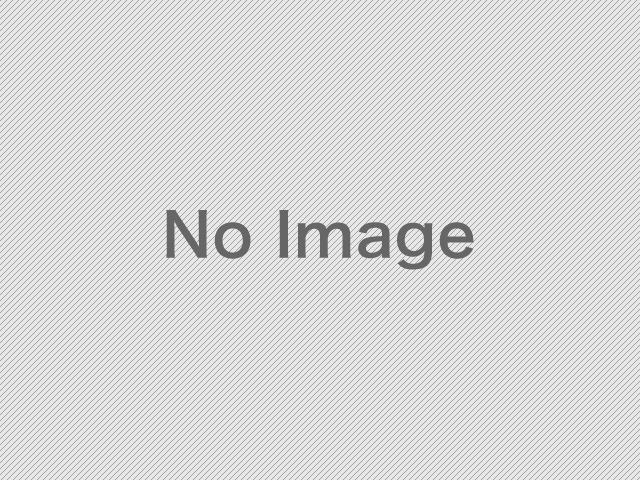 外国人歌謡の歴史ガイド記事
外国人歌謡の歴史ガイド記事3位白虎隊の哀愁を感じさせる、堀内孝雄「愛しき日々」
年末時代劇「白虎隊」の主題歌としても知られています。小椋佳さんの作詞、堀内さんの作曲のこの作品は、しっとりとした曲と物悲しい歌詞で白虎隊を彷彿とさせます。戊辰戦争の史実を思いながら聴いてみると、さらに歌詞の深さに気づかされます。
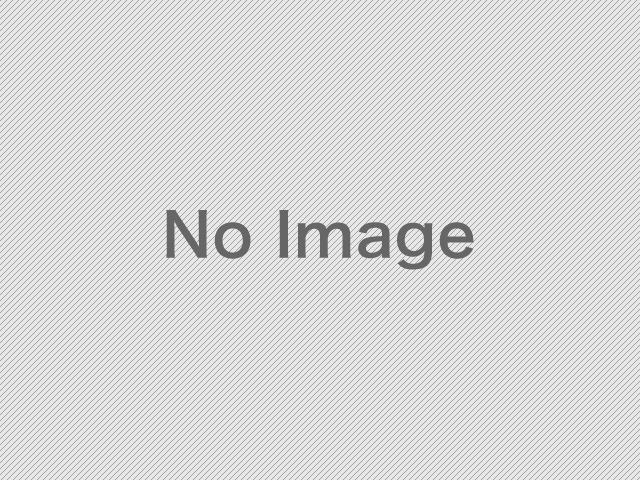 口コミでおすすめの80年代歌謡曲投稿記事
口コミでおすすめの80年代歌謡曲投稿記事4位尾崎紀世彦の歌唱力は?歌がうまい男性歌手 ベスト5
尾崎紀世彦をはじめとして、歌唱力に優れた男性歌手5人を紹介する。一番歌がうまい歌手は誰か?一度は疑問に思うはず。今回、あくまで中将タカノリの価値観を信頼してくださる読者の方に、1980年代までに活躍した男性歌手の中から「最高峰」と信じる5人を解説したい。
 演歌・歌謡曲関連情報ガイド記事
演歌・歌謡曲関連情報ガイド記事5位世界に羽ばたく『ズンドコ節』
田端義夫、小林旭、ザ・ドリフターズ、氷川きよし……時代を超えて歌い継がれ、今またレ・ロマネスクやピンク・マルティーニの活躍によって世界中で注目されている『ズンドコ節』。その起源からスピリット、ジャズやロックなど現代音楽ともなじみやすい音楽的特徴までを中将タカノリが徹底分析。
 演歌・歌謡曲入門ガイド記事
演歌・歌謡曲入門ガイド記事6位ザ・タイガース森本太郎の70歳記念インタビュー
2016年11月18日に70歳を迎える森本太郎。グループサウンズブームを代表するスターとして、一人のミュージシャンとして、ザ・タイガース時代から現在にいたるまでのさまざまな思い出とこれからを語った1万字超えのロングインタビュー。
 ガイド記事
ガイド記事7位西城秀樹をスカウトした伝説のマネージャー上条英男
西城秀樹や舘ひろしなどの1960年代から1980年代にかけて日本の歌謡曲、ロックシーンで活躍した名だたるスターたちを自分一人の手腕でスカウトし、デビューに導いた男がいる。その男の名は『上条英男』
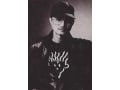 歌謡曲 あの人この人ガイド記事
歌謡曲 あの人この人ガイド記事8位歌謡曲は死んだのか?
『歌謡曲』という言葉はすっかりすたれてしまった。1990年代初頭に『J-POP』という無味乾燥な言葉にその座を追われて以来、凋落はいちじるしく、今では社会的な存在感はほとんど無に等しい。歌謡曲は死んでしまったのか? たしかに言葉としては死にかけている。しかし、むしろかつての歌謡曲らしさを備えたJ-POPは近年になって数を増やしつつあるのだ。
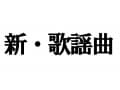 現代によみがえる新・歌謡曲ガイド記事
現代によみがえる新・歌謡曲ガイド記事9位小林真インタビュー
今回インタビューするのは『小林劇団』三代目座長、小林真。あえて時代錯誤な表現をするが、ファンの大半を女性が占める大衆演劇業界にあって小林真の芝居は“男でも観ることの出来る芝居”だ。浮わついた時流に流されず、あえて険しい道を進むことは真の実力者にのみ許されるロマン。この男、只のドン・キホーテではない。
 大衆演劇ガイド記事
大衆演劇ガイド記事10位橘菊太郎・龍美麗インタビュー 後半
今回インタビューするのは『橘劇団』総座長、橘菊太郎と『スーパー兄弟』総座長、龍美麗。つながりの深い劇団同士とはいえ、世代の離れたこの二人を同時に扱うことはきわめて異例だ。後半では「ご祝儀」や「日替わり公演」、「お酒の飲み方」の是非など業界のアンタッチャブルにあえて言及している。
 大衆演劇ガイド記事
大衆演劇ガイド記事